私たちについて


私たちの想い

海藻消滅の危機
かつては日本各地で年間100億枚も生産された海苔が、今やその半数に。美味しいおにぎりやお味噌汁の主役、海苔の生産がなぜこんなに減ってし まったのでしょうか?
有明海や瀬戸内海、三重湾といった名産地では、海苔の質と量が大幅にダウン。その主な原因は、地球温暖化による海水温の上昇です。高知県では、黒潮の影響で早いペースで海水温が上がり、重要な海藻の生産が激減 してしまっており、日本各地で海苔だけでなく、他の海藻も絶滅の一歩手前です。
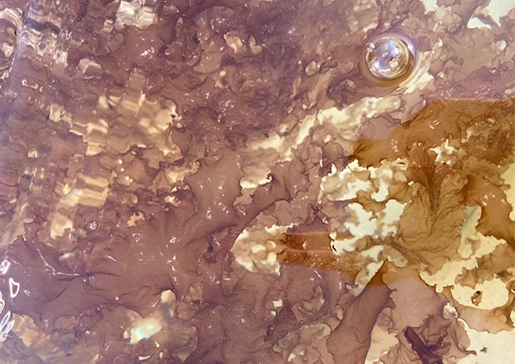
画期的な陸上養殖技術「高知式」で
海藻産業が変わる
高知大学の平岡教授が開発した「高知式陸上養殖方法」は、特許を取得した海藻種苗の作成技術を基に、各種海藻に最適な養殖用タンクと育成方法を組み合わせた革新的なシステムです。
全国20箇所以上でこのシステムが導入され、稼働中の陸上養殖設備は、特に青のり(スジアオノリ)の生産に大きな成果を上げています。
数年前に激減した天然養殖の青のりの生産量を、このシステムが補っています。
さらに、この方法は海苔(スサビノリ)を含む様々な海藻の生産にも応用が期待されており、海藻産業の未来を形作る重要な技術として注目されています。

未来の持続可能な資源
海藻はその高い生産効率で、バイオマス資源としても大きな注目を集めています。当社が開発を進めているミナミアオノリは、30度という高温の海水でも成長が可能で、1日に4倍の重量増が期待できることが研究で明らかになっています。これは、現在知られている植物の中で最速の日間成長率です。
海藻は光合成を行い、二酸化炭素を吸収して成長します。増加したバイオマスの重量は固定した二酸化炭素の量とほぼ等しいとされ、これによりミナミアオノリの栽培は、実質的に二酸化炭素を有用な素材に変換するプロセスとなります。当社では、このミナミアオノリをゼリーの素材、化粧品の原料、健康食品の成分として活用する研究を進めており、さらにはこのバイオマスを石油の代替素材として利用する可能性も探求しています。
アオノリで地球を救う
健康と地球のサステナビリティ
私たちは、健康と地球の持続可能性を守ることをビジョンに掲げています。地球温暖化による環境の変化は、自然や生態系に大きな影響を及ぼしています。特に、日本の海域では海水温の上昇が顕著で、これが海藻をはじめとする海洋生物に大きな変化をもたらしています。これにより、おにぎりに巻かれる海苔、お好み焼きに使われる青のり、佃煮に使われるあおさのりなど、栄養価の高い海藻の不作や品質低下、価格高騰が起こっています。
持続的な資源の活用
高知大学で開発された陸上養殖技術を採用し、環境変化に強い新しい養殖方法で海藻を持続的に栽培しています。この技術により、アオノリ(ミナミアオノリ)は高温でも生育可能で、わずか2日間で最大16倍まで成長します。この持続可能な養殖方法は、減少傾向にある青のりの生産量を補い、将来的には石油の代替素材としての利用も探求しています。
カーボンニュートラルへの貢献
陸上養殖技術を用いて「のり」を持続的に生産し、栄養価の高いスーパーフードとして提供することで、健康的な生活をサポートします。大量の「アオノリ」を生産することで、CO2をアオノリに吸収させて有用な素材に変換させ、これらを新たなサステナブルな素材として活用します。これらの取り組みを通して、私たちはカーボンニュートラルな社会の実現に貢献します。
